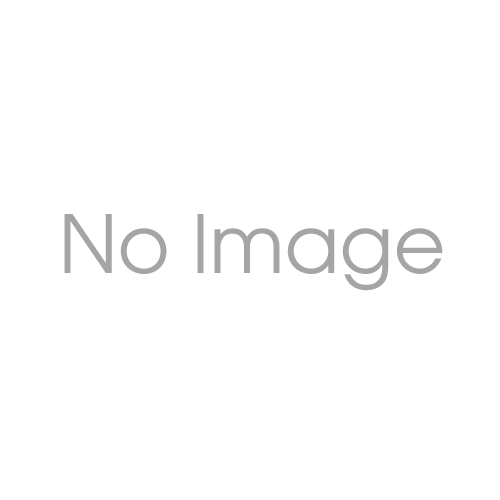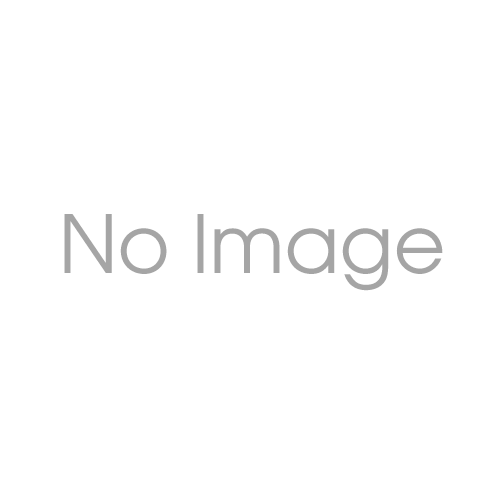【あらた/PALTAC/プラネット】商品情報の一元管理へ新会社

あらた、PALTAC、プラネットの3社は共同で、化粧品、日用品など一般消費財の商品マスタを一元管理し、製配販の流通プロセスで共同利用する新会社「株式会社プロダクト・レジストリ・サービス」を設立する。11月10日に会社設立、来年4月からサービスを開始する予定。これに先立ち10月20日、東京都千代田区の帝国ホテルで会見を開き、各社トップ、新会社の役員らが設立の目的や今後の方向性などを説明し、広く業界標準化へ向けた取り組みへ意欲を示した。
会見では、プラネットの坂田政一社長が新会社設立の背景について説明に当たった。
「流通業界において一体化された商品情報の必要性は年々高まっており、1980年以降、テキスト情報が管理され、棚割では商品画像が活用されるようになった。そして今日、Eコマースの台頭で高性能な画像、動画、複雑な商品パッケージ情報など、高度で多様な情報が求められている」とし「一方で物流の現場では、AIやロボットの活用などDX推進が不可欠となっている。これらを有効に機能させるには正確かつ最新の商品マスタ情報が欠かせない。更に、喫緊の課題である物流2024問題への対応においても、フィジカルインターネット構想の実現には、信頼できる正確な商品情報が必要なタイミングで共有されることが極めて重要な要素」と述べた。しかし、商品情報は手作業による加工やメンテナンスによるミスが発生し、情報更新に合わせたタイムリーな情報維持が必要で、情報の授受のタイミングが多岐にわたることで業務が煩雑になるなど、管理の難易度が極めて高い状況にあるのが現状。
今後、情報の正確性と鮮度を業界レベルで整備していかなければ、将来的には消費者が必要な情報を得られず、必要な時に商品を購入できなくなる恐れもある。出資する3社は、この課題を解決し、一般消費財流通の発展を支えるのは情報インフラの構築にあるとし、かつ、業界の発展に不可欠と確信したとして、経済産業省の「商品情報連携標準に関する検討会」と連携し、設立に合意した。
あらた、PALTACという全国卸とプラネットの3社でスタートすることの意義について坂田社長は「大きな意味とシナジーがある」といい「両社は合わせて年間2兆円を超える売り上げ、1000社以上のメーカーと取り引きを行っているため自然に商品情報が集まってくるポジションにある。圧倒的な商品ボリュームと流通現場における深い知見は、データベースの実効性と普及に不可欠」と評価。更にプラネットには20万SKU以上の商品情報を一元管理しているデータインフラの知見があり、大手卸の量と知恵、プラネットによるデータベースの構築、運営の専門性を組み合わせることで、データの鮮度を維持し続ける未来志向の商品情報データベースの運営を可能にすると説明した。
業界各社に広く参加を呼びかけ業界各社に広く参加を呼びかけ
経産省が商品情報プラットフォーム構想で掲げる商品情報5原則(消費者に対する商品情報の説明責任、共通情報での協調、ブランドオーナーによるシングルインプット、一括取得・共同利用、一意に識別可能な商品の共通IDの利用)に沿った正確な商品情報、製配販の全プロセスで共同利用できる、業界横断的なプラットフォームを構築していく構え。 業界全体のサプライチェーンの利益に資する仕組み、制度を確立することを目指すという観点から、全国化粧品日用品卸連合会(全卸連)との連携も視野に入れ「業界全体に広く賛同と参加をお願いしていく」(坂田社長)考えだ。
新会社の社長に就任するプラネットの松本俊男副社長は、新会社の事業概要と事業戦略を説明した。松本氏に加えて、あらたの西尾将義常務執行役員営業本部長、PALTACの山田恭嵩取締役専務執行役員営業統括本部長が新会社の役員として名を連ねる。株式出資比率は、あらたとPALTACが30%ずつ、プラネットが40%。事業内容は「一般消費財の商品情報の収集・蓄積・メンテナンスによる一元管理」「メーカー、卸売業、小売業・情報サービスベンダーに対する商品情報の提供とそれに関わるコンサルティング」「メーカーに対する商品情報登録インフラの提供とそれに関わるコンサルティング」「商品情報管理・提供のためのインフラ構築」。短期的には、商品情報登録率86%以上の達成、全ての卸への商品情報連携の開始、経産省の方針に沿った小売業への商品情報連携の定着などを目指す。また中長期戦略として、商品情報登録率100%を目指す他、卸の更なる生産性向上に向けた商品マスタ登録の統一化・標準化、Eコマース・庫内作業ロボット・フィジカルインターネットなど、効率化を推進する業務の拡大、ESG視点に基づく経営指標に対する定量的効果を提供することなどを掲げた。
これにより、初年度の売上高目標は1・1億円、3年目2・4億円、5年目2・5億円を目指す。登録メーカー数はそれぞれ900社、1200社、1500社と拡大を図る。
続いて、出資企業のトップとして、あらたの東風谷誠一社長、PALTACの吉田拓也社長がコメントを寄せ「1年半ほど前から検討が始まり、ここで発表できることをうれしく思う。流通業界でDXを進めていく上で、正確な商品情報は重要な基盤。業界各社それぞれが管理していたが、この領域では独自性を持つものではなく、競争すべきものではない。サプライチェーン全体で重複作業が発生しているが、この課題を解決するには業界全体で取り組むべきと考える」(東風谷社長)、「新会社設立のポイントは三つ。一つは連携・協働。二つ目は業界の生産性向上。三つ目はAIやDXの活用。これらについては、まずは商品の情報やデータベースは同じものを共有して、かつタイムリーで正確であることが全ての基礎となる。新会社が目指すのは、個社の利益ではなく業界全体の発展であり、3社が手を携えて、大きなビジョンに向かってまい進していきたい」(吉田社長)などと述べた。更には、オブザーバーとして出席していた全卸連の森友由会長(森友通商)も、新たな事業に対する期待の言葉を述べ「今回の取り組みが日用品化粧品業界全体にとって更なるメリットをもたらすことを祈念している。プラネット様の設立当時の、全体の発展を願う利他的な志と理念を発展的に継承していただき、小規模の卸売業も含め業界により大きな価値をもたらしてくれることと期待している」と期待のほどを表した。
(詳細は「日用品化粧品新聞」10月27日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)