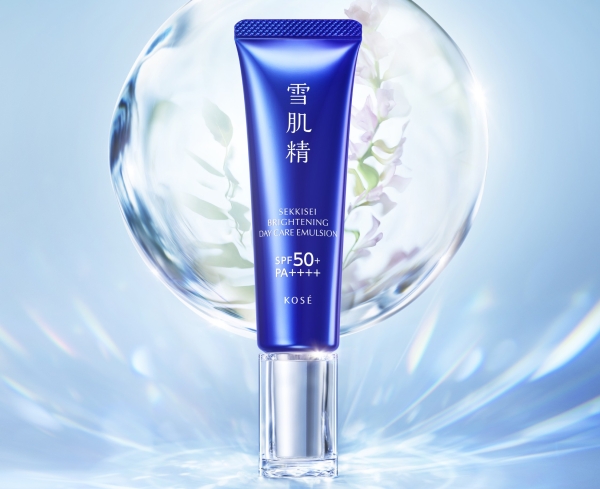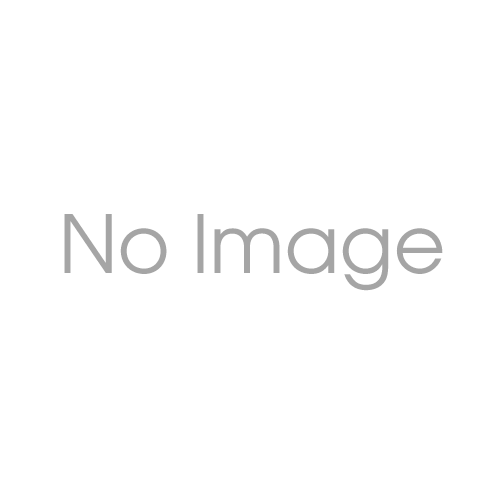【拠点探訪・エビス本社工場】自動化で叶える多品種〝変量〟生産、今後の成長戦略に弾みへ
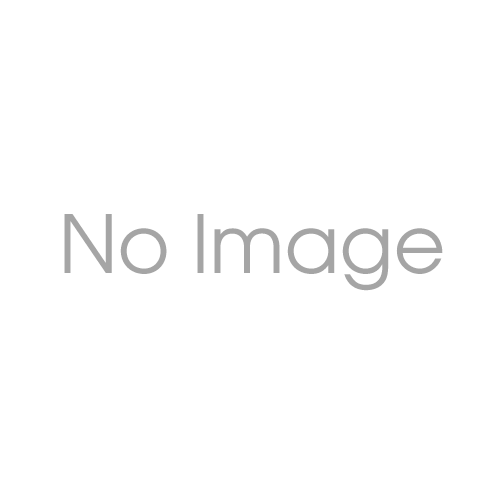
生産能力は従来より約3割拡大して年間1億本に迫る規模に
コロナ禍の影響で一時的に足踏みが続いたハブラシ市場も、ようやく回復する局面に入りつつある。幅広ヘッドハブラシの分野でナンバーワンシェアを誇るエビスは、第2工場棟を一部に公開した。より高付加価値化、また多様な品目の生産が求められる中、これらに対応できる強力な施設を手に入れたことで、今後の成長戦略に弾みがつきそうだ。
奈良県大和郡山市に本社を置くエビス。併設する工場は同社にとって最大規模の生産施設だ。2016年に第1期工事、21年に第2期工事を完了し稼働を開始した。西名阪自動車道・大和まほろばスマートインターチェンジのすぐそばに立地し、この高速道を走る車からは建屋に配置した「EBISU」のロゴが明確に見えるのだという。
合計の投資額は1期と2期合わせて90億円ほど。生産能力は従来より約3割拡大して年間1億本に迫る規模となったが「自社製品も、OEM生産のPB商品も、それぞれ品質や機能性が高まり、同時に工程が増えるなど、より高度な生産体制が求められるようになった。生産能力そのものにはまだ余力があるが、いわば多品種”変量”生産を目指してレベルアップを図っている」と乾正孝社長は強調する。消費者や販売先のニーズ、あるいは自社の新たな提案が広がるのに合わせて、様々なアイテムを量的な変化も含めてつくれるようになることが重要というわけだ。
そのためAI技術やIoTを活用した最新設備の投入を促進。4フロアにわたる各生産工程をつなぐ自動化ラインは、その象徴と言える。
4階建ての工場のうち、1、2階は成形フロアで、原料からハブラシのハンドル部を製造する。4階の植毛フロアでは、このハンドルに植毛したり、その毛をカットしたりする工程を行う。できたハブラシは3階の包装フロアでパッキング、箱詰めして出荷する。これら一連の作業において、タブレット端末を用い今の稼働状況を捉えて解析すると共に、設備異常の予知も可能だ。資材搬送システムを活用し、受入検収、整合性の確認、資材を垂直に運べるバーチレーターで包装フロアへの自動搬送も行う。
各フロアでの入出庫が可能な超大型の自動立体倉庫を
各フロアでの入出庫が可能な超大型の自動立体倉庫を備えているのに加え、それぞれに自動搬送車が縦横に行き来しながら運搬しているのが特徴の一つ。
更に各フロアで目立つのは、作業する人員が少ないこと。前記のように自動化を進めてきた結果、できる限り無人化を実現する方向に近づけている。一方で、よりクリーンな環境を保つ工場として、衛生・清潔管理も徹底しているのが分かる。
完成した製品の検品体制も抜かりが無い。例えば毛先のチェックなどは目視で行っており、訓練を積んだ作業員がハブラシを数本ずつ手に取り、それぞれに目を光らせる。生産の各工程は徹底して自動化を図る反面、最後に人間の能力を生かした体制とすることで、顧客の信頼向上にもつながっていると言えそうだ。
生産の現場を見て理解を深めてもらおうと、地元を始め周辺地域の小学生らを招いての工場見学も行っている。見学前には、キャラクターを用いてハブラシの歴史や生産工程を分かりやすく紹介した動画を流す時間を設けた。その上で現場を見てもらうことで、より理解が高まるという。そしてハブラシはもとより、オーラルケアについてもっと関心を持ってもらい、更にはものづくり自体への興味や関心も持ってもらえればという狙いもある。
乾社長は「あわよくば、見学してくれた子供たちがいつかここで一緒に働きたいと考えてくれるような、そんな工場にしたいと願っている」と語る。そこには、ハブラシの生産、供給を通じて多くの人々や社会に貢献したいという思いが込められている。オーラルケアと健康についてますます関心が高まる中で、その役割は一段と大きくなりそうだ。
(詳細は「日用品化粧品新聞」2月6日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)


冬虫夏草.jpg)