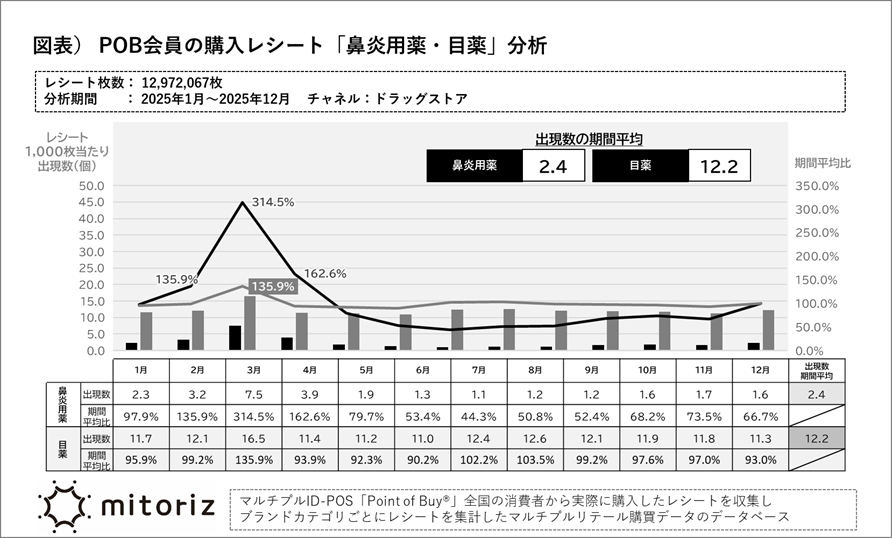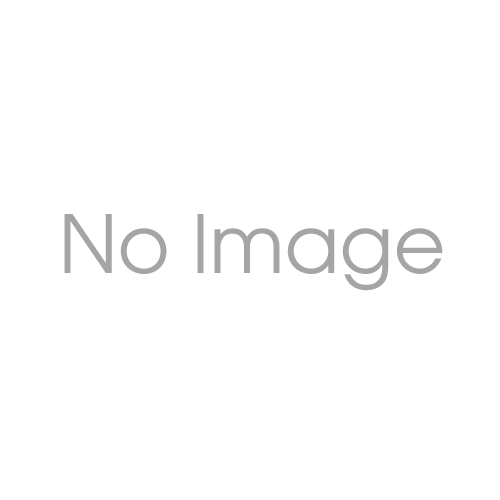【夏季特別号2024】各業界、上~下半期への課題

コロナ禍が明け、値上げの動きが顕著になり、更に昨今の猛暑、物流2024年問題など、社会的な動きや環境の変化が、日用品・化粧品業界にも様々な影響をもたらしている。解決に向かっている課題もあれば、これから解決に向けて取り組みを急ぐべきもの、あるいは先々に期待を抱かせる事象なども含め、今年下半期の動きは各方面で更に活発化しそうだ。
値上げ後の市場動向
原材料やエネルギー価格の高騰、更に物流費、人件費、その他様々なコストの上昇は、多くのメーカーに商品価格の値上げを決断させた。卸売業、小売業と各流通段階への転嫁も「食品業界などが先行していたこともあり、当初の予想より比較的早い段階で進んだ」(中堅日用品メーカー)と見られる。
現行の商品のまま価格を引き上げる単純値上げは、当初から関係者の間で成功が難しいとされていたこともあり、基本的には商品改良、これに伴うJANコードの変更、また何らかの価値を付加した上での価格改定が中心となったことは周知のとおり。「価値転嫁」「戦略的値上げ」といった表現が用いられ、各社ベースでは一定の成果を挙げたところもある。世の中あげて値上げムード一色に染まったこと、あるいは担当官庁の要請もあって「新たな価格の浸透へ向けて、大小の苦労はあったが、受け入れ性は高かった」(同)と言う。
値上げ自体は昨年、あるいは一部ではそれ以前から行われてきたが、今年に入って実際の荷動きはどうだったか。大手メーカーの推計によると、主要な日用品約30市場の全ての単価が平均1割ほど上昇。しかし、販売個数が前年を上回った市場は3分の1以下で、多くの市場で2~9%の減少となっている。結果として、金額ベースでの実績が前年に満たない市場まで出てしまっているのが現状。
コロナ禍で需要を伸ばした市場でその反動が続いていることも否定はできないが、企業と同様に生活環境が厳しくなることを懸念した生活者の「買い控え」が最大の要因であることは否めない。
必需品が多い市場だけに、買い控えがいつまで続くかという議論はさておき、まずは需要喚起する、生活者からすれば買いたくなる使いたくなる商品、サービスの提供が何より優先されるべきだろう。新ブランドか、新商品か、従来品の改良であっても、いずれの場合も生活者のニーズに応える、新たな提案が必要というわけだ。まずは今後の製配販の施策に期待が寄せられるところだ。
増える訪日客
国内消費がくすぶる中、コロナ禍を経て再び増加の一途にある訪日外国人の動向も話題になった。政府観光局の発表では、今年1~6月に日本を訪れた外国人は約1778万人で、前年比で7割近い増加。このままのペースで行けば年間3000万人を超えるものと見られる。国内人口の4分の1に相当する人数で、短期滞在者が多いとはいえ、各市場の動向にも少なからず影響をもたらしそうだ。
これを見越して、化粧品分野では主要ブランドがインバウンド需要の取り込みを狙い、ドラッグストアでは免税品売り場の拡張、充実を進めている。そうした売り場には、女性に限らず多くの訪日客が立ち寄る光景がよく見られるようになった。OTC医薬品分野も、店頭に戻りつつある訪日客へ向けたプロモーションを強化中だ。
日用品分野は、対象となる商品が少ないためか、一部を除いて需要喚起の動きが活発とは言い難い。訪日客の傾向を分析し、潮流を捉えた上で、ビジネスチャンスを探りたいところだ。
(詳細は「日用品化粧品新聞」8月1日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)