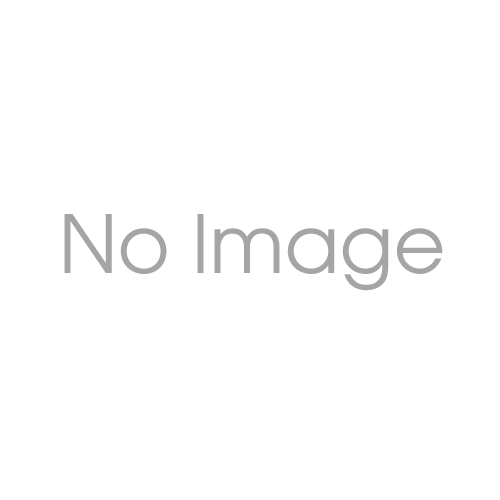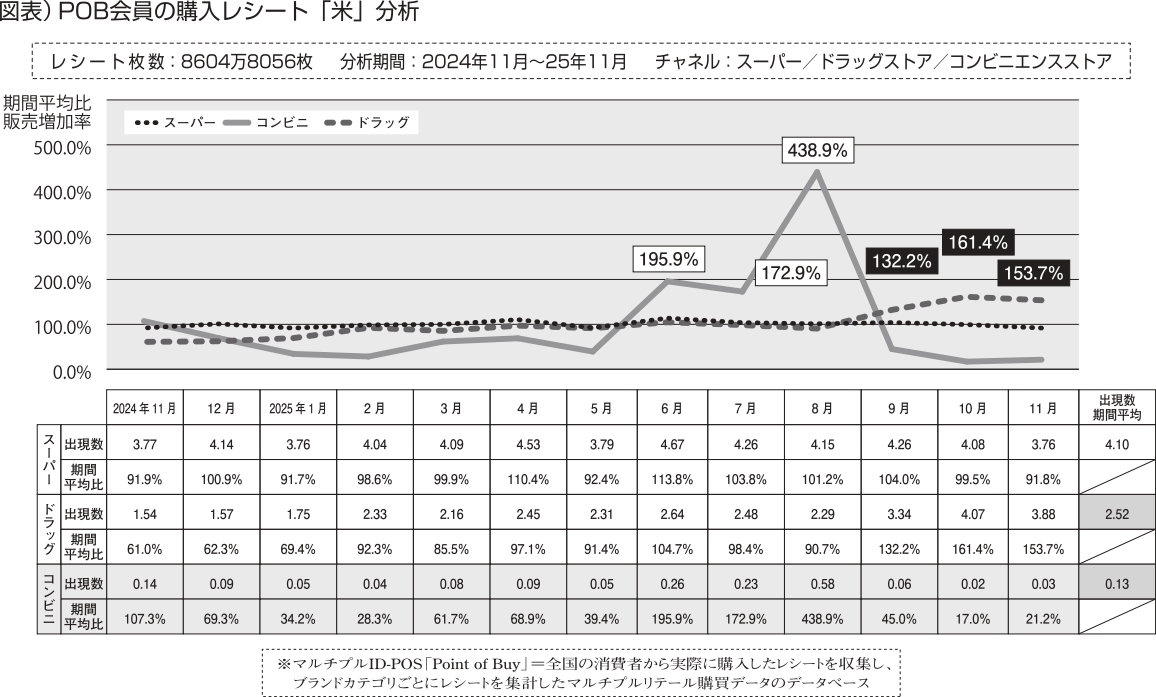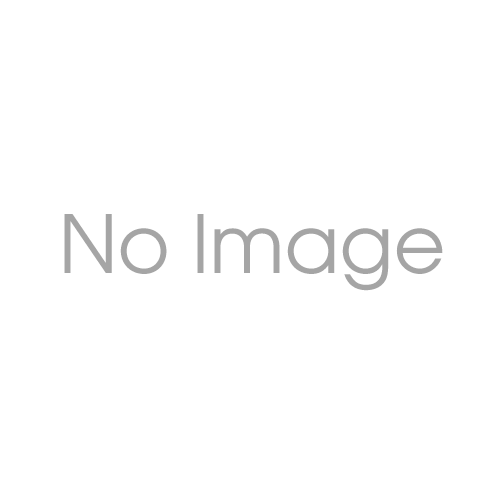【浄水器市場】カートリッジ中心に順調推移

コロナ禍で在宅時間が増えたことから快適な室内空間を求める人が増え、ライフスタイルを充実させる様々なカテゴリーが伸長したことは記憶に新しいところだが、その一つが浄水器。浄水器本体の出荷台数は近年、年間400万台を上回る堅調な推移を見せている。コロナ直後の伸長の反動がやや見られるものの、パイの拡大にはつながっており、それを証明するようにリピート客を取り込んでいるカートリッジは伸長が続き、年間3000万台を超える規模にまで成長している。
メーカー各社ではこの春も、積極的な商品展開で更なる市場成長を目指している。三菱ケミカル・クリンスイはシンプルさにこだわった「CBシリーズ」から「CB026」を投入。従来モデルから2倍の期間となる6カ月使用できる浄水カートリッジを搭載し、優れたコストパフォーマンスで若年層の取り込みを図る。
大学生や新社会人など、若年層をターゲットに長寿命モデルを展開するのは東レも同様。こちらはポット型で、交換目安を従来品比3倍の6カ月とした長持ちカートリッジ「PTC.SLV」、更にこれを搭載したポット型浄水器「トレビーノPT307SLV」を発売する。
BRITA Japanは、ブランド最小サイズのポット型浄水器「リクエリ」の新色「パウダーブルー」を展開。こちらも、これまで浄水器を使ってこなかった人との接点拡大への期待が大きい。
また、ここに来て浄水器への関心の高まりに拍車を掛けているのが、暫定目標値を超える物質が検出されたという報道があるPFAS(有機フッ素化合物)。浄水器協会では、PFASの一種であるPFOS及びPFOAの浄水能力試験方法を策定し、浄水器協会自主規格「JWPAS.B」に収載した。メーカー各社でも自社商品の試験を行い、除去能力のあるものについてホームページなどで発信している。ある関係者は「ユーザーの知識も増えてきており、問い合わせの内容などもより細かくなってきた」と明かす。
なおPFASについては環境省が、暫定目標値としている1リットルあたり50ナノグラムを水道法上の「水質基準」に引き上げる。来年4月からは自治体や水道事業者にPFASの濃度が基準を超えた場合、改善を法律で義務づけるようになる。各メーカーからの更なる発信力強化も期待されそうだ。
その他にも法制化、基準化などが進んでいる事例は見られ、浄水器協会では現在、サーバー形浄水器の製品規格化について原案作成委員会を立ち上げ、消費者団体や各省庁などとの意見交換を行いながら審議を進めている。自主規格を既に定めている浄水シャワーについても、製品規格化などを見据えた動きがある。協会では「正しい評価が正しい製品づくりにつながる」という思いから、アトピッ子地球の子ネットワークと共同で、浄水シャワー使用による皮膚、頭皮、毛髪などに関する研究アンケート調査を実施。効果を感じるという声を得ており、更なるカテゴリー活性化のヒントにつながる試みにもなっている。
(詳細は「日用品化粧品新聞」4月7日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)