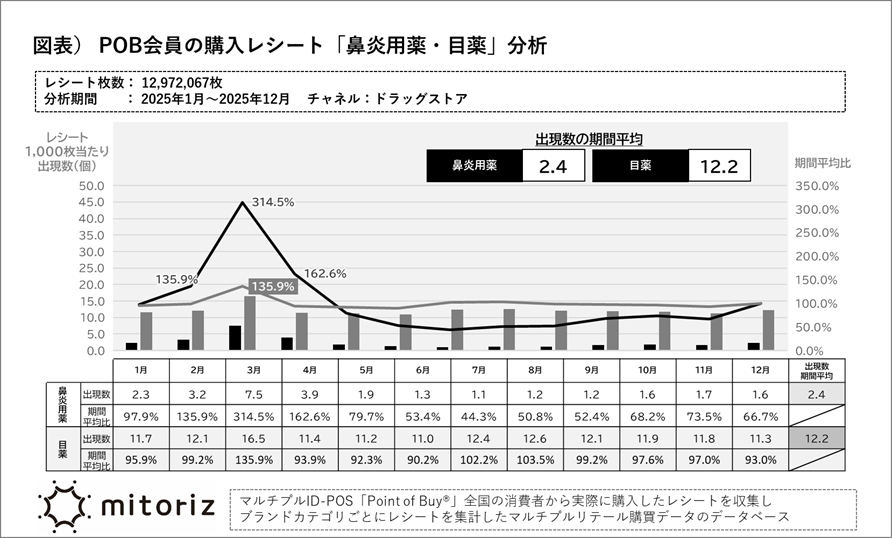主要各社決算/環境変化と戦略性色濃く

値上げ、猛暑、コストダウン
大手卸売業、メーカーの直近の業績がまとまり、それぞれに現在の状況を色濃く反映する結果として表れた。新型コロナ感染症の5類移行、長く続いた猛暑、原材料の高騰、それに伴う値上げなど、様々な環境変化の中で、PALTAC、あらた、花王、ライオンの決算から、この先の市場動向を占ってみる。
PALTACの中間決算(4~9月期)は、売上高、営業利益、経常利益などいずれの項目も前年同期を上回った。売上高は5・1%増で、金額的には半期で285億円ほど上乗せになった計算だ。理由として挙げられているのは、外出機会の増加に伴う化粧品、医薬品、その他の関連商材の販売が堅調に伸びたこと。また、異例とも言えるほど長期にわたった猛暑の影響で季節品、夏物商材の動きに拍車が掛かったこと、あるいはインバウンド需要回復もプラスに働いた。
売り上げ増に伴い利益も増加したが、更に注目されるのは販管費率で、前年同期の5・20%から0・13ポイント引き下げ5・07%となった。一部は前期までの一過性費用とはいうものの、ローコスト物流を生かした取り組みが販管費率を改善するキーになり、変動費の上昇を抑えつつ固定費の吸収効果を発揮したと言える。
あらたの中間決算(同)も増収増益を果たした。売上高、経常利益共に過去最高という。売上高は5・9%増、金額にして260億円余りを積み上げた。こちらは、大容量品や高付加価値商品の売り上げ増に加えて、原材料費高騰に伴う値上げや専売・優先流通品の拡大が奏功した。従来、注力カテゴリーとして位置付けてきたヘルス&ビューティーやペット関連が成長を見せ、更にはコロナ需要の変化に対応し、マスクや除菌シートなど関連商品が減少した分、人流や外出機会の増加による化粧品などの需要を捉えた形となった。
販管費率は8・11%ながら、前期より0・13ポイント改善された。新人事制度の導入で社員の給与水準を高める一方、庫内や業務の生産性向上で人件費率を抑えている。
卸売業大手2社の決算にはいくつかの共通点があるが、中でも販売の拡大を目指す「攻め」と、徹底したローコスト化を図る「守り」のバランスに長けているのが特徴的。いわば経営の基本に忠実に取り組んでいるという印象だ。
メーカーの決算はどうか。花王の第3四半期(1~9月期)決算は、売上高0・2%減、営業利益34・1%減と厳しい数値が並んだ。理由は明確で、コロナ禍を経て国内事業は回復の兆しを見せているものの、中国などアジアの一部で厳しい状況に置かれていること、また、構造改革へ向けた費用を計上していることが挙げられる。日本国内のコンシューマー事業は、一部市場の低迷から影響を受けたライフケア事業が微減だった以外、全ての分野で実質増収。これがアジアでは逆にライフケア以外は全て減少している。中でも化粧品の減少幅が大きく、市場は減速しながらも回復基調にはあるが、現地の人気ブランド「キュレル」がプロモーションを中止するなど販促活動の抑制が響いたと分析する。
ただし、国内では衣料用洗剤やUVケアで付加価値の高い新商品を投入、また戦略的値上げを着々と進め増収につなげている分野も多く、通期での業績予想は変更していない。
ライオンの第3四半期(同)は、売上高3・5%増ながら、事業利益、税引前利益は4割以上の減少となった。減益は、競争費用の増加や本社移転に伴う費用の発生などがあったこと、また昨年1月に土地の譲渡益を計上した反動も影響した。
一般用消費財の売上高を見ると、主力のオーラルケア分野は一部ブランドで販促の内容を見直したことで全体としてわずかに減収となったが、衣料用洗剤と柔軟剤で大型新商品を相次ぎ投入したファブリックケア分野は6・2%増と好調だった。市場動向の変化や戦略的な取り組みが結果として表れたと言えるが、更に今後の施策に期待が寄せられる。
(詳細は「日用品化粧品新聞」11月13日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)