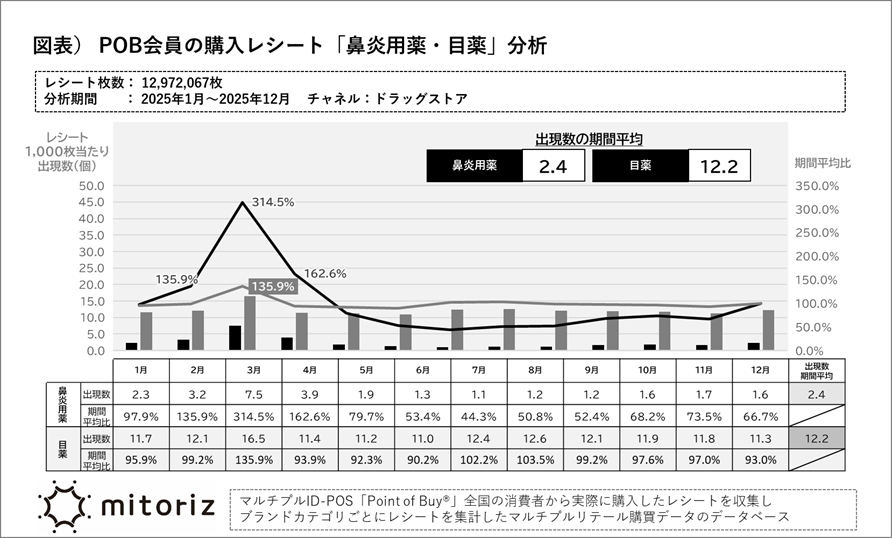【大木ヘルスケアHD】秋冬用提案商談会開催、全68種提案

大木ヘルスケアホールディングスは6月17、18日、東京都大田区の東京流通センターで秋冬用カテゴリー提案商談会を行った。引き続き、メーカーの単独ブースによる新商品提案ではなく、新たな市場を製配販で創出する提案を強め、来場者にフルアテンド型の紹介を行うなど密度の濃い提案会として、社会背景も含めた具体的な店頭展開事例を全面的に打ち出した。
提案カテゴリーは、これまで同様「快適生活」「園芸/ペット」「医薬品」「健康食品」「コンタクト&補聴器」「コスメ&バラエティー」、更に近年力を入れる「フェムケア」の7種。全68提案を、87社の共同提案、282社の商品協力のもと示した。
主な事例では「快適生活」では、引き続きノルディックウォーキングやシナプソロジー、またセルフチェック機器の活用など店頭発のイベントを紹介。その他、累計販売本数200万本突破のオリジナルハブラシ「モフらし」の定番コーナーでの提案を推し進めた。「園芸/ペット」では、ドラッグストアの売り場に欠けている、ペットのオーラルケアや、熱中症対策飲料などを提案した。
「医薬品」では、子供のQOL向上に向けた「こどものおくすり箱」や、夜尿症などのトイレ悩み対策品、腸活サポート医薬品などを紹介した。
「健康食品」では、たんぱく質の悩み別チャートを用いた「たんぱく迷子」向け売り場などを提案。「コンタクト&補聴器」は、ワンデーレンズを中心に、好評を博すお試しレンズの更なる拡充や、ニーズが高まる小容量10枚入りの展開をアピールした。
「コスメ&バラエティー」では今年のトレンドワードともされる、長寿を意味する「ロンジェビティ」志向を、各年代に合わせて打ち出すなど、新市場の創出を狙った。「フェムケア」では、更年期の女性の症状に加え、男性の更年期需要を開拓することで、女性市場の更なる深耕を図る。また「企業内から啓発を」を掲げ更年期の症状が季節ごとに違うことなどへの理解を深める必要性を説いた。
開催2日目の18日、松井秀正社長が会見を開き、提案商談会の主旨や、小売業関係者に認知を望む今後の重要なポイントなどについて説明した。
松井社長「当社の提案商談会は、営業マンによるフルアテンド型を以前から取り入れており、そのため来場者も絞って、1組4時間ほどかけて、展示物をベースにした提案を行っている。
以前はOTC中心の医薬品、健康食品、化粧品などにおいて、ドラッグストアはこうあるべきだ、という提案を強めていたが、ドラッグストア、GMS、スーパー、ホームセンター、EC、ディスカウントストアなど業態の垣根が崩れ、それぞれの企業のヘルスケアに向き合う姿勢や果たす役割が変わってきている中、画一的な提案では対応が難しくなっている。そこで、展示物をベースに、企業ごとに営業マンが提案を変えている。それが当社として最も存在感を発揮できる道でもある。
今回の提案商談会の展示では、私の意向もあり、商品の紹介はあまりしていない。人口減少や高齢化、労働力不足といった社会背景や今後の動向などの大枠を示し、具体的な店頭展開については、当社の営業マンが補完するという前提で、その企業ごとに合った提案を進めている。
また、社会背景を説明することで、小売業の方々と危機感を共有する狙いもある。我々が軸足を置くヘルスケアの観点でも、人口減少、高齢化の中、医療保険制度をこのまま維持できる可能性は低く、また地方自治体の維持も難しい。更に地域包括ケアに目を向けると、国は指針を出し、研究結果などを共有するなど、あくまでサポートするという立ち位置にある。地方自治体も消滅の危機にある中、地域包括ケアは国民が自分たちで構築していかなければならない。『自分たちの健康だけでなく、地域の健康も自分たちで助け合いながらやってください』というのが国が示す地域包括ケアの前提である。ただ、現時点でケアの仕組みはまだまだ形になっていない。これは危機感がこれまで共有できていなかったことに他ならない。そのため、この提案商談会で皆様と危機感を共有し、生活基幹業態のドラッグストアとして、地域包括ケアの推進、実現のみならず、日本の保険制度の維持に向けた提案を強化している」
(詳細は「日用品化粧品新聞」7月1日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)