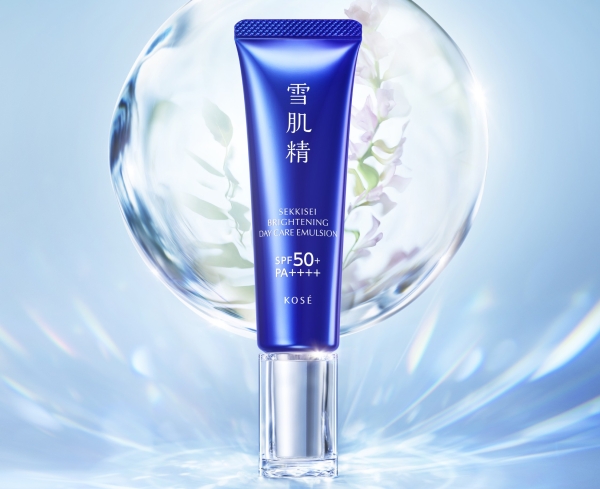【マスク市場】ファッション性の価値、どう維持・拡大するか

2022年度は拡大傾向、今年4月以降の動きに注目
マスク着用が自己判断に委ねられるようになり3週間が経った。コロナに対する規制は各方面で緩和され、また、感染についての報道も減り、日々の暮らしがコロナ前に戻りつつある。そんな中、マスクの市場動向はどう変化し、今後どのようになっていくのか。業界関係者に話を聞いた。
マスクの市場規模を見ると、2019年度は、年度後半の1月からコロナ需要が始まった約1200億円(当社推計)に拡大し、感染爆発のあった20年度は約3000億円に膨れ上がった。店頭は欠品が続き、輸入物の増加、異業種大手の参入、価格の跳ね上がりなど「店頭の混乱」という言葉だけでは片付けられない状況に陥ったことは記憶に新しい。
21年度は、約2380億円と落ち着きを見せたが、それでも19年度に比べれば約2倍の規模を維持した。
22年度も、前年度に続き更なる反動減が考えられたが、4〜12月の前期比は、5・5%ほどプラスで推移。年度後半の1〜3月は、自己判断に委ねる旨の発表及び導入があったが、業界関係者からは「今年は花粉の大量飛散で需要が高まったこと、また、家庭内在庫が潤沢で、着用緩和になったからといって販売量はそう大きく変わらない、という見込みから今年度はプラスで着地するのでは」という声が聞かれる。
しかし、業界関係者がその後に続けるのは「新生活が始まる4月以降や、気温が高まる夏場以降、変化が必ず出てくるはず」といった言葉だ。
2022年度はプラスの着地予想。新生活の始まる4月以降、どういう動きになるか
これは世の中の着用緩和の動きから致し方ないところだろう。現に、23年1〜3月の時点で売り場を縮小している小売店、アイテムを絞っている小売店は多く、先の言葉通り、4月以降、潮目が変わってくるのは間違いないだろう。
小売・卸売関係者の間では「今年は昨年の7掛け、もしくは5掛けを想定している。既に、輸入物などの投げ売りも散見されており、店頭価格全体が下がらないかとの懸念がある」として、取り扱いに慎重になる企業も少なくない。
ファッション性を求める顧客が多いロフトでは「マスコード」(サンスマイル)のようなファッション性のあるカラーマスクは引き続き好調だが、全体の売り上げはやはり少しずつ落ち着きつつあるという。東京・渋谷の店頭も、売り場は縮小、今後もカラーマスクを中心に売り場を構築していく予定という。
新たな需要をどこまで掘り下げられるかで市場動向が変わる
取り扱いアイテム絞る傾向に。ファション性あるカラーマスクの動向に注目
22年度の市場の拡大は、メーカー側がカラーバリエーションを拡充、ファッション需要を開拓したことに加え、使い捨ての不織布が推奨されたこと、また、外食などでマスクを外す機会が増え一日で何枚か付け替える人が増えたことなどによる出荷枚数の拡大が主に要因として上げられる。 これまで小売業は、多様化する需要に応えるために、取り扱いアイテムを増やし、また、生活雑貨・アパレル系店舗も取り扱いを拡充させるなどしてきたが、ここに来て、それらを絞る、あるいは生活雑貨・アパレル系店舗では取り扱いをやめるといった傾向が顕著になっているようだ。 「企業の特性もあると思うが、ドラッグストアなどでは、大手の立体などの付加価値品と、PBを含めたスタンダードなプリーツの箱物、それとカラー・バイカラーのマスクを、売れ筋を絞ってそろえる店舗が多いようだ。一時、店頭は『どれを選んでいいか分からない』というほどだったが、消費者が選びやすい状況がつくられつつある。また、単に『着けていればいい』という消費者心理も拡大していると思われ、これまで好調だった高単価の商材は動きが鈍くなっている」(メーカー関係者)。
高単価品の動きが落ち着きつつある中、ファッション性のあるカラーマスクについては、復調するインバウンドに強い企業、立地の店舗では、取り扱いを拡充する向きもある。小顔に見せたり、顔色を良く見せたりするカラーマスクは「感染対策」とは異なる価値をこれまでに構築した。新たな売り上げの潮流になっているとも言える。人々がマスクを外す機会は確実に増えると思われる一方、マスクを外すことに抵抗のある人はまだまだ多く、マスク姿の自分の顔に慣れてしまった人も多いことだろう。コロナが収まって以降、通常の白いマスクの売り上げは落ち着くだろうが、カラーマスクのような新たな需要をどこまで掘り下げられるかで市場動向が変わることは考えられる。そういった流れをどう店頭で表現していくかが、ここ数年の一つの鍵になりそうだ。
(詳細は「日用品化粧品新聞」4月10日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)


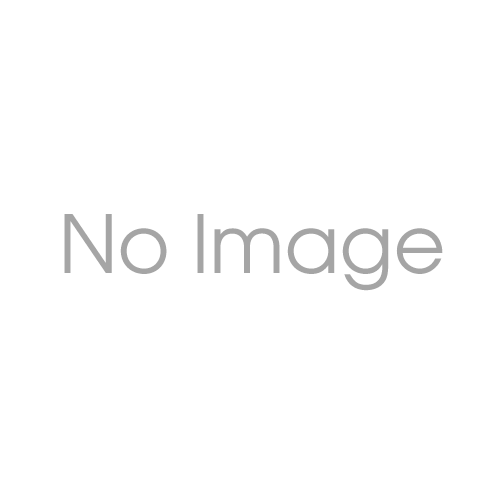
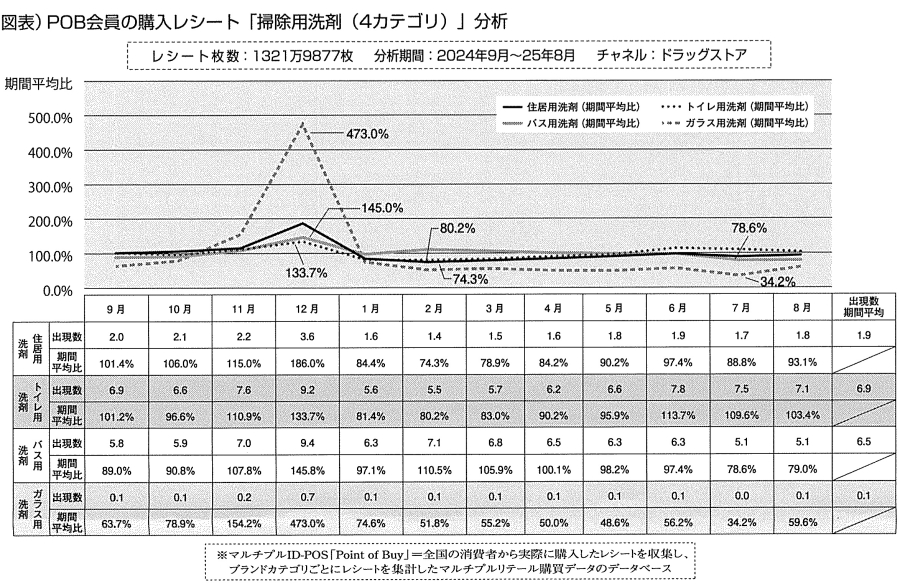

冬虫夏草.jpg)