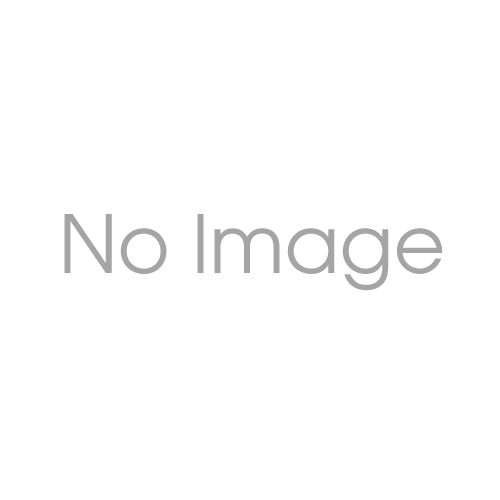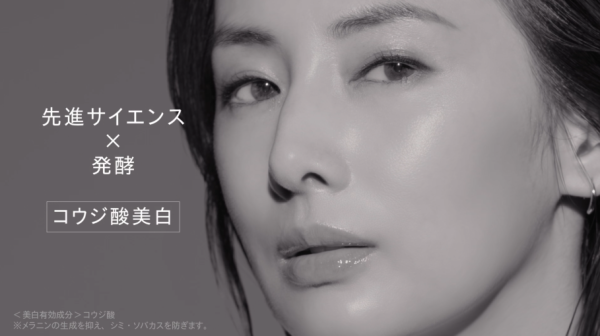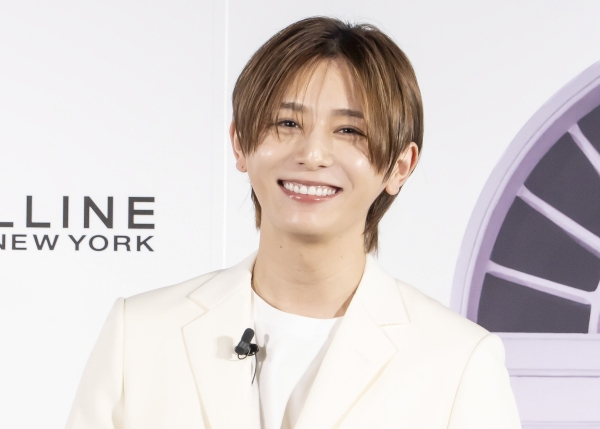【特別インタビュー・サラヤ 更家悠介社長】「衛生・環境・健康」で更なる時代開拓を

手肌と環境への優しさをコンセプトのヤシノミ洗剤」
1952年の創業以降「衛生・環境・健康」を授業の柱として、様々な商品やサービスで人々の暮らしを支えてきたサラヤ。商品展開だけでなく「ビジネスを通じた社会問題の解決」をキーワードに、アフリカ・ウガンダでの衛生改善活動やボルネオでの環境保全活動、RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)への日本に籍を置く企業としての初入会など、他社とは一線を画す独自の路線を常に歩んできた。今年70周年を迎え、更なる飛躍をどういった形で目指すのか。更家悠介社長にこれまでの状況や今後の方向性などを聞いた。
——創立70周年を迎え、感慨深いものがあると思います。社長に就任されて以降のこの20年を振り返っていかがですか。
「2000年代は、ボルネオでの環境保全活動など、サラヤとしての社会貢献の基盤ができたように思います。しかし2010年以降については、特に変化の激しい10年でした。2010年代は、アフリカでの事業に着手しました。ウガンダでの『100万人の手洗いプロジェクト』を始めたのは2010年です。周辺諸国では現在、ウガンダの他、エジプト、ケニア、チュニジアの4カ国で事業展開しています。2010年代の後半には、ヨーロッパへの進出も開始しました。企業買収なども含め、現在は4カ国で事業展開しています。2000年代はボルネオでの環境保全、2010年代はアフリカ、ヨーロッパに進出し、2020年以降は新型コロナによる大きなインパクトを受けた、この20年間はそういった印象に残る出来事が多かったですね」
——代表ブランド「ヤシノミ洗剤」は昨年50周年を迎えました。改めて発売のルーツを聞かせてください。
「元々、当社はヤシ油を使った手洗い石鹸液をつくっていました。そこから事業が広がる中、ヤシ油を使った植物性洗剤などを学校給食などの業務用として取り扱っていたのですが、それを家庭用の洗剤として販売したのが始まりです。当時、石油系合成洗剤による河川汚濁が社会問題になっていました。そこで学校給食の現場の方から使用感への高い評価をいただいていた手肌への優しさと環境への優しさをコンセプトとしたのが『ヤシノミ洗剤』です。時代や生活者ニーズに合わせて、成分やパッケージなどのリニューアルを何度か行っていますが、基本的なコンセプトは変えていません」
——50年前に発売した商品が今なお第一線でユーザーを拡大しているのはすごいことですね。 「近年では、お客様から環境に優しい洗剤ということで注目いただき、今も安定した動きを今も見せています。『ヤシノミ洗剤』は、食器用洗剤では日本で初めて詰め替えパックを発売したブランドです。そういった環境に対するレガシーは、今も当社のサプライチェーンへの考え方やセールス&マーケティングの面で生かされていると思っています」
RSPO参画、ボルネオ環境保全活動も
——御社といえば、ボルネオの環境保全活動も、企業や商品の認知を高める一因になりました。 「2004年頃に『ヤシノミ洗剤』とボルネオの熱帯雨林の環境問題の関係性が取り沙汰されました。当社としてもそれを受け止め、2005年にRSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)に参画し、2007年からは『ヤシノミ洗剤』の売上金の1%をボルネオ現地の環境保全活動に役立てています。皆様の協力で保全活動は継続しており、今後の拡充も視野に入っています。商品をメッセンジャーにし、お客様と目的意識を共有できたことは非常に良かったと感じています」 ——NPO法人ゼリ・ジャパンの「ブルーオーシャンプロジェクト」に協賛するなど、海洋汚染の防止にも積極的です。
「ボルネオの環境保全を陸とすると、陸と海はつながっているわけですから、海の保全にも着目しなければなりません。国内でも、海岸に漂着するプラスチックゴミは相当な量で深刻な問題です。その削減に少しでも貢献したいと思っています。2025年の大阪・関西万博では『ブルーオーシャンパビリオン』が出展されますので、共創パートナーとして当社も参加する予定です」
——環境に対する取り組みが非常に目立ちます。重点事業として捉えているのでしょうか。 「環境ももちろん重要ですが、当社のメイン事業はやはり衛生となります。医療衛生や食品衛生、公衆衛生など、様々なアプローチがありますが、新型コロナの影響でここ2、3年は手指消毒剤やディスペンサーなど感染対策用品の引き合いが強まりました。環境事業に比べ、一般消費者へのアピールがまだ弱いので、今後は情報発信を更に強化していきたいと思っています。主戦場は、日本を始めとしたアジア、アメリカ、ヨーロッパで、最近は競争相手も増え、品質のレベルも上がってきました。アフリカは、決して裕福とは言えない土壌でいかにビジネスを行っていくか、啓発を含めて展開を広げている段階です」
——社会的には、環境面も衛生面もニーズが非常に高くなっています。SDGsという言葉が生まれる以前から力を入れてきたのは先見の明によるものですね。
「結果的にニーズに合っていたということはあるかもしれません。温暖化や食料危機、石油エネルギー危機などは我々の生活にも響いてきますし、決して対岸の火事ではありません。企業活動にSDGsの観点を取り入れていたことはある意味、必然的な流れです。ボルネオの環境保全活動開始当初は、SDGsという言葉もありませんでした。SDGsが誕生する以前の2012年に、コーポレートスローガンを『ステイヘルシーアンドスマイル』から『いのちをつなぐ』へと変更しました。先見の明というより、常に問題意識に対応してきた結果かもしれません」
——売上規模が順調に伸びていることがうかがえます。ブランドの育成も着実に進んでいますか。
「売上高は順調に伸びており、昨年は1000億円に達しました。内訳は国内約700億、海外約300億円。国内だけで1000億になれば、マーケットでの存在感はある程度しっかりしたものになると思うので、まずはそこを目標にしています。ブランド別では『ヤシノミ洗剤』に加え、天然洗浄成分を配合した洗浄剤『ハッピーエレファント』や天然ハーブ配合の無添加シリーズ『アラウ.』『アラウ.ベビー』も拡大しています。その他、自然派甘味料『ラカント』も近年、伸びが目立っています。また、オーラルケア商品『クルクリンPGガード』を発売し、本格展開を始めました。他にもオーラルケアでは、グループ内に医療法人の歯科医院を設立しました。合わせて大阪大学と組んで、歯周病予防への効果が明らかになっているクルクミンの研究を進めているところです」
——昨年、今年と新工場の竣工が続きました。来年以降の予定については。
「現在、茨城工場の第2期工事が進行中で、竣工は来年3月を予定しています。医薬品関連を扱う工場で規模も大きく、稼働後の状況に期待しています。国内では医療向けのマスク工場を、中国では医療用のニトリル手袋工場を稼働しました。コロナ禍を通じて、衛生事業の生産や管理を自社でコントロールすることが重要だと感じたことが、立ち上げの背景にあります。その他、エジプトとチュニジアで工場を現在建設中です」
——次の時代に向け、新たな健康事業も開始したと聞きます。
「食と運動を連携させたヘルスケア事業を新たに始めています。大阪を中心に、現在5箇所にレストランとトレーニングジムを併設したもので、スタジオやジムで体を動かして、隣接するスペースで栄養バランスに優れた食事を取ってもらうというサービスです。活動を通して知見も上がってきていますので、今後の商品開発に生かせればと考えています。健康に関しては、これまで『ラカント』を通じて消費者とコミュニケーションを取ってきましたが、健康にはいかに予防が大事かを痛感しました。本サービスでは、ただ単に体に良いとされるものを提供しても効果的ではないので、科学的な根拠を取り入れて提案しています。健康経営を打ち出す企業も増えているので、業務用ルートとして展開することも視野に入れています」
——今の若い社員に向け、求めたいこと、必要と思うことはなんでしょうか。
「『自分で考える』ことを求めたいですね。例えば、新型コロナの時の働き方など、企業としてガイドラインは作成しますが、後は自分の頭で考えて行動してくださいということです。人の言われた通りにやって取り替えしがつかなくなることは珍しくありません。最後は自分の責任と判断が鍵になる。常日頃、そういった考え方を身に付けてほしいと思っています。また、当社は毎年、50人ほどの新入社員がおり、若返りが進んでいます。社内の雰囲気もずいぶんと変わりました。若い世代には、バーチャルの体験が浸透してきていると思いますが、個人的にはリアルの体験、体感を大事にしてほしいと考えています」
——最後に、70周年を迎えてひと言お願いします。
「当社は、衛生・環境・健康を事業の柱にしていますが、生活者や社員、また、環境の全てが元気にサステナブルに次の世代につながっていくことを願っています。我々のビジネスはお客様あってのものです。70年を迎えられたのは、お客様のおかげですし、お客様へのバリュー提案は、卸売業様、小売業様の協力無しには成り立ちません。当社は、現在も推進中の事業が多々あります。業界関係者の皆様には、事業へのご理解とご指導をこれからもお願いしたいと思っています」
(詳細は「日用品化粧品新聞」6月6日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)


ホームページ用 各社トップ2026 (002).png)