【圧力鍋協議会・伊藤会長に聞く圧力鍋市場の今】コロナ禍以降、微減で推移

コロナ禍のおうち時間の増加で、規模の成長が見られた圧力鍋市場。特に、使い勝手が良く手軽に調理ができる電気圧力鍋が市場をけん引、ユーザーの裾野拡大に大きく貢献した。その勢いも、コロナが明けた昨年から落ち着き始めたが、現在はどのような動きを見せているのか。圧力なべ協議会の伊藤彰浩会長(ワンダーシェフ)に市場の状況や今後の見通しなどを聞いた。
【圧力なべ協議会・伊藤会長に聞く】
――今年の圧力鍋市場の状況はいかがでしょう。
「市場規模の一つの目安となる製品安全協会のSGマーク申請枚数は、前年比3%減と微減でした(今年4~9月)。電気圧力鍋は、コロナ禍で伸びた反動もあり厳しい状況です。通常の非電気圧力鍋は多少持ち直してきていますが、電気の減少をカバーするには至っていません。業務用は、外出機会の増加で回復傾向にありますが、当協議会はSGマーク貼り付け範囲の10ℓまでの商品を対象としていますので、大容量の業務用の動向によって、方向性や取り組みが大きく変わることはありません」
――協議会の会員社によって好不調の差は見られていますか。
「高価格帯品を百貨店などで販売している会員社、中間価格品を広く販売する会員社など様々ありますので、社会の状況に応じて多少の差は出てきます。最近では、高価格帯品はそこまで落ち込んでいないことから、百貨店での対面販売など圧力鍋の良さを伝える場があれば、チャンスが広がる可能性はあると思っています」
――消費者に広く理解してもらいたい圧力鍋の良さはなんでしょう。
「光熱費の上昇や、共働き世帯の増加によるライフスタイルの変化には、圧力鍋による省エネ、短時間調理といった特長が効果を発揮できるものと思っています。最近では、コンビニなどの惣菜や冷凍食品への支持が集まり、調理をしない人が増えています。一方では、自分の手でつくりたいという人も一定数おり、圧力鍋はそういった層に特長や効果をしっかり認識していただけているはずです。圧力鍋だからこそ出せるおいしさ、柔らかさを、SNSなどを使って伝えていければと考えています。もちろん、実際に商品に触れられる販売店の関係者の方の協力なしには、市場の活性化は実現できません。店頭で多様な圧力鍋をお取り扱いいただけることが重要です」
――情報発信は会員社がそれぞれで進めるべきなのでしょうか。
「協議会で決めた方向性をベースに、各社なりのやり方でアピールしていくのが理想ではないでしょうか。例えば、夏でも適した圧力鍋による料理があること、また、暑い夏だからこそ時短調理でキッチンに立つ時間を短くできること、冷めたい蒸し鳥なども短時間で簡単に調理できることなどを訴求し、売り上げ増につなげているメーカー様もあります。圧力鍋は、ふたを外せば普通の鍋として使えますし、当然、ふたを付ければ圧力鍋として使えます。そういったポテンシャルを考えるとまだまだ普及率は低いと考えています」
――大手家電量販店などでは、家電製品を新中古品として販売するビジネススタイルも構築されつつあり、非電気、電気圧力鍋もそういった場で売られるケースが増えてきました。それに関する問題などは。
「圧力鍋は、消費生活用製品安全法という法律に基づいてつくられた製品です。つまり、消費者が使う際に注意が必要ということです。また、当協議会は元々、商品の安全性を追求し、安全に使ってもらうことを目的に立ち上げられました。そういった状況から、メーカー及びメーカーが認めた修理業者がメンテナンスしたものでないと補償することができませんし、現状、万が一のことが起こった際の責任の所在が明確ではありません。その見解を会員各社と共通認識にしています」
――市場発展に向けた課題や方向性をひと言。
「圧力鍋を使ってもらわないことには、市場の発展はあり得ません。今は、入り口として、使い方が簡単な電気圧力鍋への注目度が高まっていますが、簡単に使える非電気の圧力鍋の開発、上市を進めてもいいのではと思っています。いずれにしても、一度使ってもらえるよう、SNSなどを通して使用を促すことが肝要です」
――協議会内での課題については。
「会員社の拡大は継続的な課題です。当協議会の会議には、製品安全協議会様も出席していますので、安全面における様々な情報をいち早く入手できるなど、入会していただくことでのメリットは少なくありません。会員社が増えれば、圧力鍋の良さをより広く伝えられます。未会員への入会の呼び掛けを強化し、業界を発展させることが、当協議会の役割だと認識しています」
(詳細は「日用品化粧品新聞」12月2日号/または日本経済新聞社「日経テレコン」で)

ホームページ用 各社トップ2026 (002).png)

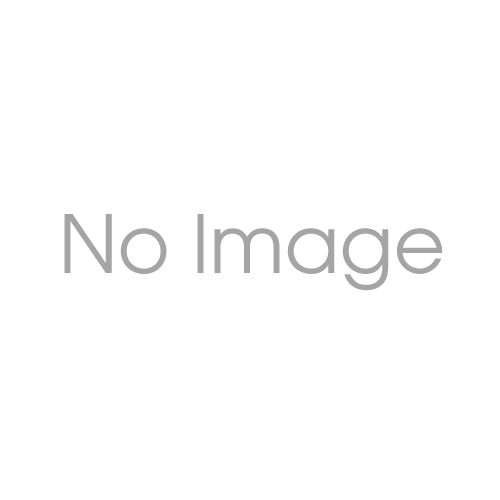
.jpg)
